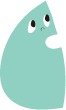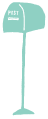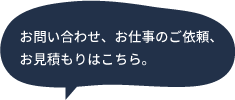Webアクセシビリティの義務化がスタートします
- WEB

ブログのタイトルにある通り、かねてから話題に上がっていた、webアクセシビリティの義務化がスタートします。
そもそもwebアクセシビリティというのは、webサイトを利用する様々な方、年齢や、体に障害を持った方への配慮して、webサイトを見やすく使いやすくするための基準を、
A・AA・AAAと三段階に分けて、定めています。
2024年(令和6年)4月、Webアクセシビリティの義務化?
webサイト制作をするにあたって、Webアクセシビリティ対応どこまですべきか?というところにいきついたりしますよね。2024年4月の義務化の施行にあたり、だいぶ表に出てきた感じがします。
とは言え、webアクセシビリティ対応ってなに?義務化って?何をどこまでするのが義務化?という疑問が湧いてきます。
義務化の具体的な経緯と背景、対応方法については、ググると様々な方々が詳しく(時には難しく)解説しているページがいっぱいあるので、そこで読んでいただければいいですが、端的にじゃあどうすればいいの?という点について簡単にまとめてみました。
-
「合理的な配慮」に関して、「義務化」
-
「環境の整備」については、「努力義務」
「合理的な配慮」とは?
例えば、webサイトが見にくくて、商品がわかり辛いんだけど何とかならないの?という問い合わせがあった場合、
その商品に対してご説明したり電話でサポートしたり、その窓口側にあたる事業者側が対応する必要がある、この対応する、というのが義務化になります。
「環境の整備」とは?
例えば、webサイトが見にくいとか、問合せしにくいなどといったという問い合わせに際して、見え方をわかりやすくするよう、例えば事業者側から制作会社に依頼し、保守範囲の中で修正を加えたり、もしくは費用をいただいて再提案・対応するというのが努力義務、ということになります。
もちろん、事前に考慮しながらwebサイトを制作するのが大事になるわけですが、
その基準になる「A」「AA」「AAA」の3段階の基準のうち一番優しい、「A」を守れるかというと、意外と難しかったりします。
レベルAに全て対応ではなく、一部準拠する、ダブルAに対しては、配慮する、今の時点では明確にお伝えしにくいのですが、必要に応じて、ご相談のうえ対応できればと考えています。